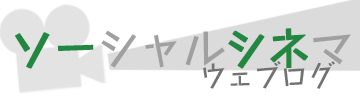今も存在する人身売買と奴隷、『ゴースト・フリート 知られざるシーフード産業の闇』はとにかく気が滅入る、でも見なければならない。
タイの漁業会社の一部には、人身売買で手に入れた奴隷労働者を使っている業者がいる。彼らは何年もの間船から降りることもできず、給料も支払われず、暴力にさらされ、時には命を落とす。そんな被害者たちを救おうと立ち上がったのは、パ
主人公の鈍感力が若者たちを目覚めさせる。『シニアイヤー』は大人こそが見るべき学園コメディ。
オーストラリアからアメリカに引っ越してきたステファニーは、高校ではイケてるブループに入り、プロムクイーンになろうとチアリーディング部に入部、見事キャプテンになり、学校イチの人気者ブレインを恋人にし、最高学年を迎える。しか
女性の手仕事をアートに昇華させたら平和への希望が見えてきた-『YARN 人生を彩る糸』
町中の柱や壁をニットで飾る「ヤーン・グラフィティ」アーティストのティナ、かぎ針編みの巨大なニットと全身ニットのパフォーマーで作品を作るオレク、白いニットを張り巡らせた舞台でパフォーマンスをするサーカス・シルクール、カラフ
アイスランドの自然の中で“獣性”を見せる人たち、大いなる自然の魅力-『馬々と人間たち』
独身男のコルベインがめかしこんで馬に乗り、子持ちの未亡人ソルベーイグの元を訪れる。村人たちは双眼鏡で遠くからその様子を見つめる。二人は惹かれ合っているようで、和やかに会話をし、コルベインはソルベーイグの家をあとにするが、
なぜおばさんが工場を攻撃?アイスランド映画『たちあがる女』の寓話的世界と世界をよくする方法とウクライナと
合唱団の講師をしているハットラは、アイスランドの草原に立つ送電線をショートさせて停電を起こし、アルミニウム工場の停止を図る。計画を成功させたハットラのもとに、4年前にしていた養子縁組の申請が通ったという知らせが来る。養子
ジャーナリストが追い求める唯一の真実とは。『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』に見るウクライナ問題の深淵
1933年ロンドン、ロイド・ジョージ元首相の外交顧問を務める記者のガレス・ジョーンズは、大恐慌下にもかかわらず経済成長を続けるソ連の財源に疑問をいだいていた。奇しくも教皇の影響で解雇されたジョーンズは、スターリンに直接尋
震災から11年、楽しく映画を見て3.11と自分との距離を見つめ直す-『永遠の1分。』
2022年3月11日で東日本大震災から11年になる。あちこちで「風化」という言葉が聞かれるように、被災地から遠い人たちの中では震災の記憶は徐々に薄れていっている。 テレビでは、震災関連番組をやるだろうが、その数は減ってい
違和感ある映像が考えさせるイスラエル社会の真実-『アヘドの膝』 #TOKYOFILMeX2021
新作映画のオーディション中のイスラエルの映画監督Yは監督作品の上映会のため砂漠の中にある小さな村を訪れる。その村出身でYのファンだという役人のヤハロムの出迎えを受ける。滞在場所となるアパートでヤハロムから上映会で話すテー
ゲイの老人が“人々”と出会い直し、豊かさを取り戻していく物語『スワンソング』 #TIFF2021
老人ホームで暮らす元ヘアドレッサーのパット、紙ナプキンをきれいに畳んで収集することと、介護士に隠れてタバコを吸うことしか楽しみがない彼のもとに、ある日、弁護士が訪ねてくる。 その弁護士は町一番の富豪でかつての顧客だったリ
平和になったコソボで女たちは男尊女卑の価値観と戦う-『ヴェラは海の夢を見る』 #TIFF2021
夫の誕生日パーティーの準備をする手話通訳者のヴェラのもとに、不動産業者から田舎の家が売れそうだという連絡が来る。ヴェラは夫にそのことを伝え、売れたら娘にアパートを買ったり家具を新しくしたいという夢を語るが、夫は曇った顔を